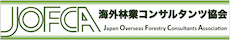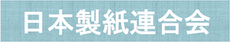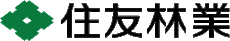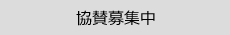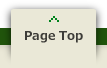森林動物関係研究の百年を振り返る
林業薬剤協会会長 小林 一三
私は1960年に森林総合研究所(当時は東京・目黒の林業試験場)に入った。今から54年も前のことである。今まで意識したことがなかったが、私の森林学会員暦はすでに半世紀を越えたことになり、このような執筆依頼を受けるのも自然の成り行きなのであろう。そうはいっても、先の太平洋戦争後の事情については比較的に楽に情報を得ることが出来るものの、戦前のことについては情報源が少なくて、まことに心もとない。幸いにも編集者の正木氏が日本森林学会誌の創刊号(1919年)からの総目次を送付してくれた。また、タイミング良く小林富士雄氏による「森林病害虫雑話(その2)江戸から明治・大正までの森林病害虫」(林業と薬剤、No.206, 2013.12)が発刊されたので、これらを参考にしてなんとか原稿を仕上げることが出来た。日本の森林動物(節足動物と脊椎動物)研究を特徴付ける大きな流れとして、20世紀初頭から社会的関心の高かった松くい虫問題、太平洋戦争後の大規模針葉樹一斉造林に多発した林業害虫対策およびその後に盛んになって現在に続いている森林生態系の中での動物の役割・生物多様性の研究がある。
現在ではマツ材線虫病(病原体がマツノザイセンチュウ、媒介者がマツノマダラカミキリ)として世界的に知られているが、その枯死・伝播のメカニズムが解明されたのは1970年前後のことであった。20世紀初頭からメカニズム解明までの間、原因不詳のまま、この激しい松枯れは「松くい虫被害」と呼ばれ、昆虫研究者の担当すべき重要課題となっていた。展望の見えない困難で長い研究活動によって、枯死したマツの樹皮下に棲息する多種多様な昆虫は健全なマツには寄生できない二次性昆虫であること、激害型被害発生地に多く発生する夏型枯損木にはシラボシゾウ属・マツノマダラカミキリ・キイロコキクイムシが優先的に寄生すること、これらの昆虫が寄生する前にマツのヤニ浸出が止まっていることなどを明らかにした。これらの成果がマツノザイセンチュウ発見の下地になったといえる。枯損原因が解明されても外来病原体による激しい病害であるこの松枯れは今後も末長く我国最大の森林被害となり続けることは確実である。昆虫が流行病の媒介者である場合には媒介昆虫をたたくのが防除の基本なので、今後とも昆虫研究者とマツノマダラカミキリとのかかわりも続いていくであろう。
太平洋戦争以前には森林保護関係研究者の数は他の研究分野の研究者数よりもかなり少なかった。森林学会誌の創刊(1919)から1928年までの10年間にこの会誌に掲載された論文数は約1000編であるが、その中で昆虫関係は4編、鳥獣関係は3編に過ぎない。矢野宗幹や小島俊文といった少数の研究者の名前が見られるのみで、他の分野の研究者数に比べると明らかに少ない。このような傾向はさらに約20年後の終戦の少し後まで続く。なお、今はまったく省みられないが、当時の朝鮮総督府林業試験場報告にはいくつかの優れた昆虫関係論文が見られる。小林富士雄氏によると、江戸から大正にかけての時代にはマツカレハの被害が多かったと言う。この時代までは森林からの有機物の過度な収奪によって全国的にアカマツ林が沢山存在し、人目に付きやすいマツカレハ被害が関心を持たれたのであろう。この傾向はマツの若齢林が減少した1970年頃まで続く
先の太平洋戦争は我国のあらゆる面に歴史的大変革を与えた。森林・林業分野では戦時中に荒廃した森林の回復が急がれた。また敗戦後の極めて旺盛な木材等の需要を満たすため、大規模な森林伐採が全国的に実施された。これらの伐採後地や草地に1950~70年の20年間、毎年20~40万ヘクタールがスギ、ヒノキ、アカマツ、カラマツなどの針葉樹人工林に仕立てられていった。これが現在の「成熟期を迎えつつある1000万haの人工林」の主体を形成している。一つの樹種の一斉大規模造林をすれば、本来の森林生態系が持つ自己修復力が失われ、必然的に様々な生物害が多発するようになる。この大規模人工林造成の功罪については様々な意見のあるところであるが、これを契機にして採種園・苗畑・新植地・未閉鎖林・閉鎖林のそれぞれの段階に棲息する節足動物や脊椎動物は林業に被害を与える害虫・害獣として、大量に増員された研究者の研究対象となり、これによって飛躍的に研究が発展したことは事実であり、防除法の開発を主目的としながらも、これによってもたらされた多種多様な研究成果が現在の我国の森林動物学の基盤となっている。
日本の主要針葉樹を加害する動物種については「農林有害動物・昆虫名鑑」(日本応用動物昆虫学会、2006年)に、マツ類:85種、カラマツ:616種、トドマツ類:65種、エゾマツ類:56種、スギ:49種、ヒノキ:32種、アスナロ:10種などの多数の種名が挙げられている。なお、広葉樹についても、この名鑑には、落葉カシ類:112種、ポプラ・ヤナギ:81種、常緑カシ類:44種、ケヤキ:35種、シイノキ類:32種などを挙げている。これほど多様な昆虫などの節足動物と野鼠、野うさぎ、カモシカ、シカ、ツキノワグマ、イノシシなどの哺乳動物の研究成果が、どのような経緯で発表されたかの一端を知るために再び「森林学会誌の総目次を調べてみよう。
1949年から1958年までの10年間にこの学会誌に掲載された論文数は約900編で、そのうち21編が害虫関係、5編が害獣関係であり、それ以前に比べるとかなり増えている。1959年から1968年までの10年間では、約800編のうち害虫関係が51編、害獣関係が2編であり、害虫関係論文の増加傾向が著しい。1969年から1978年までの10年間に約900編の論文が掲載された。この時代になると鳥獣関係論文が15編と急増してきた。この増加傾向は今日まで続いている。また、マツ材線虫病に関する研究が活発に実施されるようになった。これを樹病関係と昆虫関係に篩い分けるのには無理なものもあるが、あえて筆頭著者の専門分野で分けてしまうと昆虫関係71編、樹病関係41編になった。これらを全て合わせると127編(全体の14.1%)になり、森林保護分野がすでに森林学のなかで重要な部分を占めていることが伺える。森林保護関係論文数が掲載総論文数の10%を越える傾向は今日まで続いている。1979年から1988年までの間にスギカミキリなどのスギ・ヒノキ成林後の材質劣化害虫の論文が目立つようになる。また、殺虫剤にたよらない生物的防除の研究も増えてきた。1989年から1998年頃になると昆虫の個体群動態と鳥獣の捕食の関係、獣類による種子散布などの森林生態系の機能解明を意識した研究成果も見られるようになってきた。害虫や害獣を対象としながらも、単なる被害防止を越えた生物間相互作用の解明など生態学的な内容の研究もこの頃から増えてきている。また、例えばマツノザイセンチュウに対する抵抗性をより深くした研究など、専門性の高まった研究も目に付くようになってきた。1999年から2008年頃には多発するようになったナラ類集団枯損の病原体媒介者であるカシノナガキクイムシについての研究成果が見られるようになった。また、この10年間にはこれまで最多の25編の鳥獣関係論文が掲載されており、関係研究陣の充実ぶりを伺わせる。
植物は有機物をつくる生産者であり、動物はその有機物を口から取り入れて栄養にする消費者、口がなくて体表面から消化液を分泌して有機物を分解し栄養をとして体内に取り込む菌類などは分解者と呼んでいる。当然のことながら害虫・害獣や益虫・益鳥獣の他に森林には実に様々な動物が棲み、森林生態系がシステムとして円滑に動く上でそれぞれの働きをしている。今後の森林動物の研究はこのような枠組みの中で進展するであろう。これまで「樹病学」とされてきた分野も分解者全体を対象に研究を進めることになると思われる。研究者の基礎的専門性が深まるにつれて、森林を舞台としながらも、その研究成果は「森林学会誌」を越えたより学術的で世界に評価されやすい学術誌への投稿も着実に増加しつつある。長期的な視点で自然と人間社会との関係を考える上で森林は非常に大切な研究対象であって、より多くの科学者が参加して研究の深化と成果の総合が進むことを願っている。
学会100年間の知の資産に戻る 
TOPページに戻る